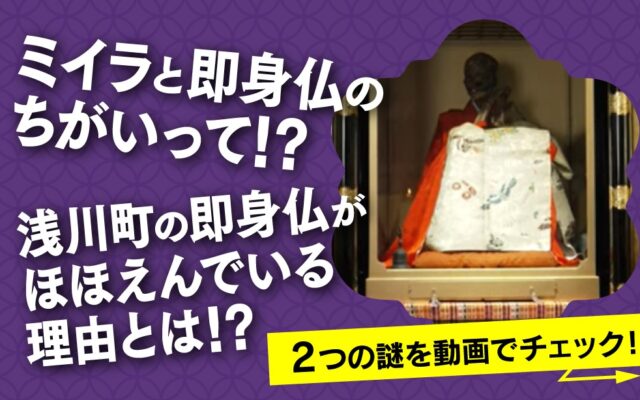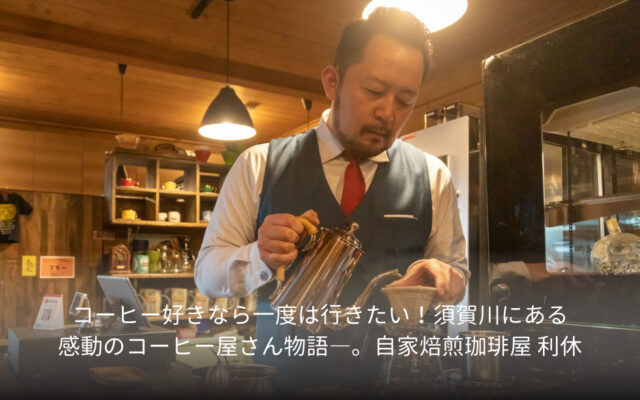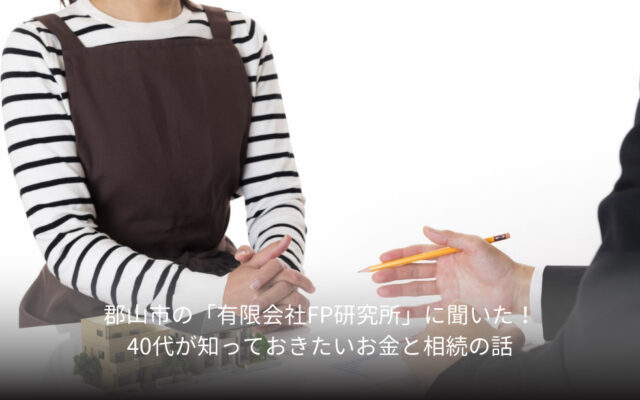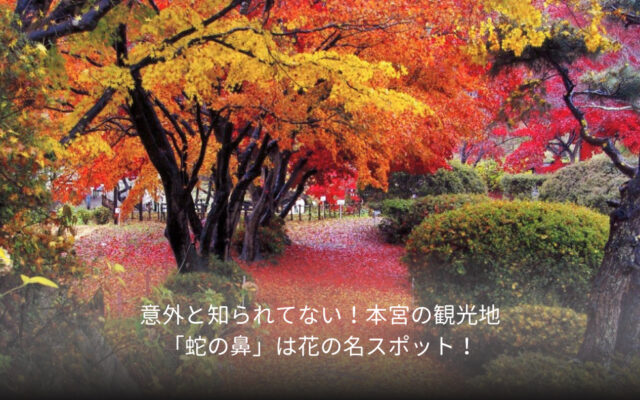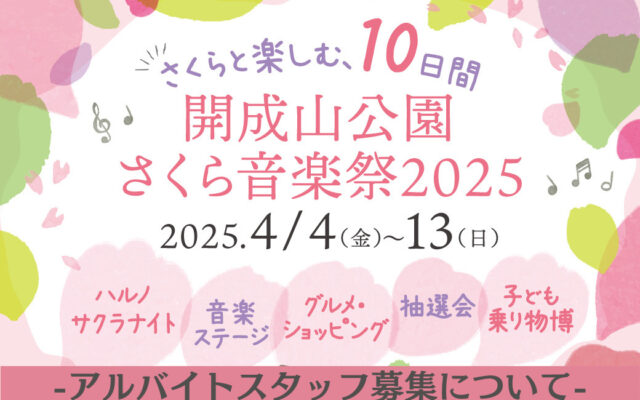東日本大震災での体験をきっかけに家業の道へ
遠藤社長はエンドウの2代目です。家業である水道事業に興味を持ったきっかけは、高校2年生の時に起きた東日本大震災でした。「自宅や近所、友人の家でも水が出ない状況が続き本当に困りました。そのとき父が、水道局の連絡を受けていろんなところで水道管を直し復旧させていることを知り、医者にも勝る仕事だと思いました」と振り返ります。一般企業で3年勤めた後、エンドウで5年間社員として現場を経験し、29歳で社長に就任。システムを活用した業務効率化を推進するなど、新しい風を吹かせています。

水道工事業のやりがいを「ものすごく多くの人に利用してもらえるサービスを作っていること」と話す遠藤社長。水道管は地下にあるため、多くの人が目にする物ではありませんが、人々の生活にはなくてはならないもの。「水道管って行き止まりがないんです。必ずどこかでつながっているので、私たちがつないでいる水道管を通った水が、全ての郡山市民に使われているといえます。これってなかなかすごいことだと思いませんか?」と笑顔で語ります。
業務効率化とキャリア開発で若手を育てる!
埼玉県八潮市では2025年に、老朽化した下水道管が原因で道路が陥没した痛ましい事故がありました。水道工事はエンドウなどの水道工事業者が自治体からの依頼を受けて行うものですが、重要なインフラを担っているからこそ、新しい人材を育て技術を受け継いでいくことが必要です。
エンドウが実践している人材育成の一つが、若手社員に対して年次ごとに目標を与え、収入や役職の変化といった具体的なキャリアビジョンの見通しをつけてあげること。「ある程度定量的なゴールを期間に分けて決めていくことは、高い意欲をもって働き続けることにつながるはず」と遠藤社長は話します。

遠藤社長が社長に就任してから、ITシステムを活用した業務効率化も進みました。担当者が月2~3日かけて行っていた給与計算は、新しいシステムを導入することで10分ほどでできるようになり、工事に関する書類の作成時間も短縮。このことで残業時間も減り、今ではあっても1日1時間程度といいます。
Vol.1の記事でご紹介した「新3K(かっこいい、休暇が取れる、希望が持てる)」の取り組みも、社員の誇りを育てる取り組みの一つ。「これから先どんなに世の中が変わっても上下水道は必ず必要。『3K(きつい・汚い・危険)』という言葉も、建設業で働いたことない外の人がイメージだけで言ってるだけなのかもしれません。イメージのせいで人手が不足するなんてことはあってはならない。だからこそ、見られ方は変えていかないといけないと思っています」と遠藤社長。
こうした取り組みが実を結び、近年は新卒・第二新卒で入社した技術職の離職率がゼロ!前社長時代から続けてきた改革が着実に実を結び、働きやすい職場を実現しています。
積極的にコミュニケーションがとれる人に来てもらいたい!
インフラを支えるという大きなやりがいを持つことができ、キャリアアップの意欲を高めながら取り組めるエンドウの仕事。新卒・中途いずれも採用を行っています。どんな人がエンドウの社風に合っているのでしょうか?
「積極的に質問ができる人っていうのは、やっぱりすごくいいなと。技術職については言葉で説明するよりも『見て覚える』という空気がまだまだ残っています。見て、まねしてやってみて失敗したとしても、何がだめなのかを考えて改善していく中で、どんどん質問してコミュニケーションを取れる人だと成長していけると思います」

水道工事業は人が培ってきた技術でしかできない、AIが代わることのできない仕事です。取材を通して、遠藤社長の水道事業へのプライドや人材育成への思いが見えてきました。Vol.4では現場で活躍する社員の方にお話をうかがいます!
※この記事は2025年3月に制作したものです。内容は取材当時のものです。